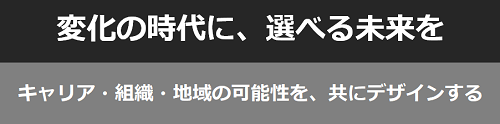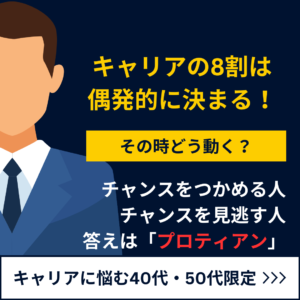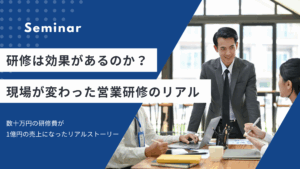プロティアンキャリアで埋めるジェネレーションギャップ──若手とマネージャーの価値観がすれ違う理由
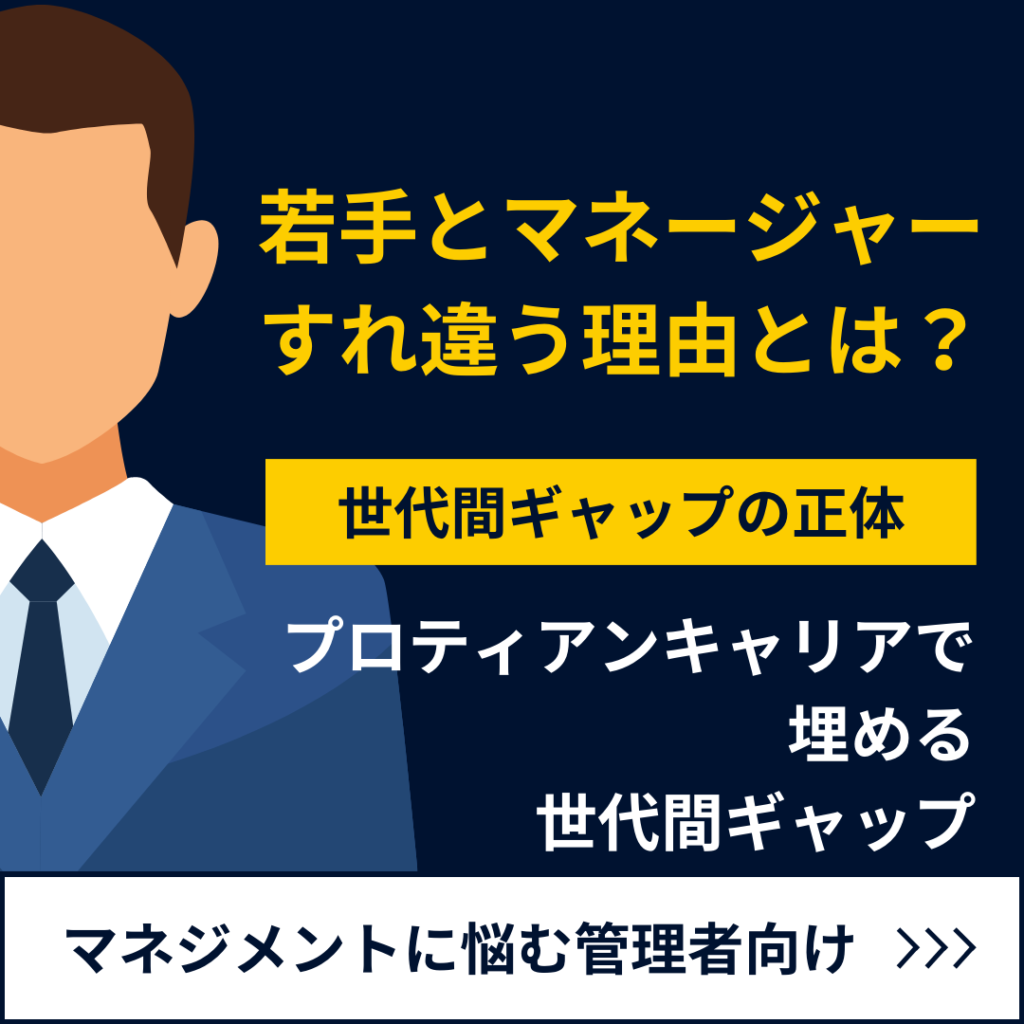
「最近の若手はすぐ辞める」
「上司の言うことを素直に聞かない」
そんな声を、マネージャー層からよく耳にする。
一方で若手社員はこう感じている。
「評価の基準が古い」
「上司は自分の価値観を押しつけてくる」
この“すれ違い”は、
ただの世代間の感覚の違いではなく、キャリア観そのもののズレから生まれている。
そのズレを解消する鍵が、「プロティアンキャリア」にあると私は考えている。
ジェネレーションギャップの正体
マネージャー層の多くは、“メンバーシップ型雇用”を前提としたキャリア観を生きてきた。
・年功序列
・終身雇用
・我慢していれば報われる
そうした価値観の中で、「努力は報われる」「組織の中で昇進することがキャリアの成功」という考えが深く根づいている。
一方、Z世代・ミレニアル世代の若手は、
・成果主義
・柔軟な働き方
・副業や転職は前向きな選択肢
といった、より“自律性”や“多様性”を重んじるプロティアン的なキャリア観を持って社会に出てきている。
つまり、
両者は前提にしている「キャリアの地図」がそもそも違うのだ。
なぜマネージャーと若手はすれ違うのか
マネージャーが「責任感」と思って語る言葉が、
若手には「押しつけ」に聞こえる。
若手が「成長のために転職を視野に入れている」と言うと、
マネージャーは「会社への忠誠心がない」と感じる。
また、上司は「背中を見て学べ」という価値観が染みついているが、
若手は「対話とフィードバック」を求めている。
このすれ違いは、“どちらが悪い”のではなく、 「キャリア観の前提」が違うだけなのだ。
この“前提の違い”に気づかずにコミュニケーションすると、組織内に「不信感」「誤解」「孤立感」が生まれてしまう。
プロティアンキャリアが橋渡しになる理由
プロティアンキャリアの本質は、 「自分の軸でキャリアを描く」という考え方にある。
これは、年齢や立場に関係なく適用できる。
若手にとっては、
「組織に頼りすぎずに自分で選べる働き方」の後押しになる。
マネージャーにとっては、
「組織の中でも、自分の意志で成長し続けられる」ことの再確認になる。
この価値観を、組織全体で共有できたとき──
・若手は「組織の中で自分らしく成長できる」
・マネージャーは「多様なキャリア観を理解して支援できる」
という“対話と理解の接点”が生まれる。
プロティアンキャリアは、ジェネレーションギャップを超える「共通言語」になり得るのだ。
管理職こそ、プロティアンであれ
組織を動かすのは、現場のリーダーたちだ。
彼らが“自分の時代の正解”にとらわれている限り、 若手との分断は埋まらない。
私自身、かつて部下との関係に悩んだことがある。
「昔の自分なら、こんなことで弱音を吐かなかった」
「なぜやり方を教えても、すぐ実行できないのか」
そんなふうに感じていた。
でも、あるとき思ったのだ。
「それは自分が正しいのではなく、相手の背景が違うだけかもしれない」と。
マネージャー自身が、まずプロティアンキャリアを実践する。
・価値観のアップデート
・柔軟なコミュニケーション
・「教える」ではなく「学び合う」姿勢
これらが、若手との信頼を築く第一歩になる。
まとめ
世代間のギャップは、放っておけば溝になる。
でも、そこに橋を架けるのが“プロティアンキャリア”という考え方だ。
若手も、ベテランも、これからは「自分の軸」で働く時代。
だからこそ、世代を越えて「変化を楽しむキャリア観」を共有してみよう。
そして何より、マネジメント層がそれを“実践する姿”を見せることが、次の時代の組織をつくる大きな一歩になるのだ。
最後まで読んでいただき感謝です。
※本文では敢えて部下・上司・管理職という言葉を使用しています。
私は普段「部下=メンバー」「上司・管理職=リーダー・マネージャー」と呼んでいます。